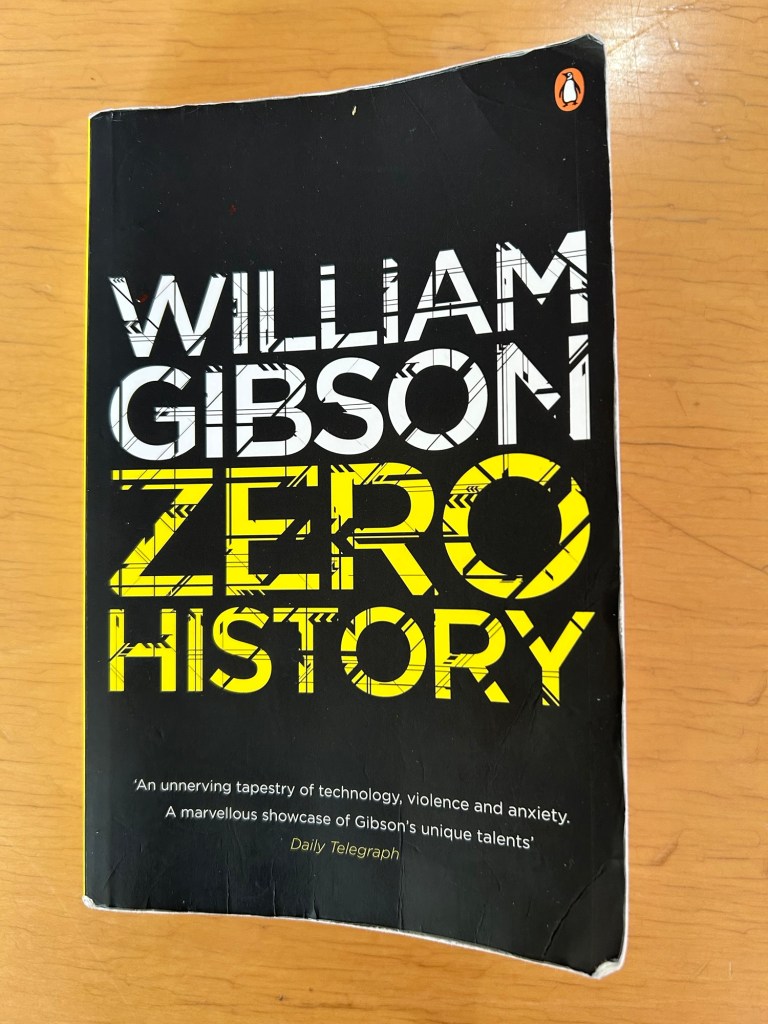
「サイバーバンク[1]」と聞いて思い浮かぶものを三つ挙げろと言われれば、真っ先に出てくるのは、ビートたけし、キアヌ・リーブス、そして1984年に出版され、サイバーバンク・ジャンルの先駆け的存在として知られる小説の『ニューロマンサー』ではないだろうか。
本書はその『ニューロマンサー』や1995年に『JM[2]』(邦題)として映画化された短編作品の『記憶屋ジョニィ[3]』等のサイバーパンク作品を世に送り出したアメリカ生まれでカナダ在住の作家、ウィリアム・ギブソン[4]による21世紀を舞台にした現代スリラー小説である。
主人公の一人はフリーランスの女性作家ホリス・ヘンリー。以前からの知り合いで、元雇用主でもある、ブルー・アントという広告代理店の経営者、ヒューバータース・ビッグエンドから、「ゲイブリエル・ハウンズ」という衣服の地下ブランドのデザイナーを探し出すように命じられる。それに関連して、その地下ブランドを世に流布させるために宣伝をあえて一切行わないという、掟破りのマーケティング手法についても調査し、その発信元を特定せよ、というミッションを受ける。
その過程でもう一人の主人公、ミルグリムと出会う。ミルグリムはロシア語に堪能で心配性のアメリカ人男性。最近はスイスのバーゼルにある高級医療クリニックで麻薬中毒の治療を受けている。ミルグリムもビッグエンドに雇われ、「ゲイブリエル・ハウンズ」についての情報収集のためにロンドンやパリへの出張を余儀なくされる。
途中、ミルグリムはウィニー・タング・ウィテカーという、アメリカ国防省傘下の犯罪捜査機関の特別捜査官の接触を受け、彼女に協力しつつ、ビッグエンドから指示された任務に取り組んでいく。
なぜジーンズの地下ブランドを突き止める事にビッグエンドはそこまでこだわるのだろうか。何者かが、その地下ブランドのデザインを使い軍事用の衣服を作成して軍需契約を獲得しようとしているのではないか、とビッグエンドは疑っているようで、彼自身似たようなビジネス展開を視野にいれていたため、その正体不明のライバルについての情報を集めたい、ということのようだ[5]。
なお、ホリスはビッグエンドとはできれば関わりたくない、と考えているものの、近年のマネーマーケットの混乱で損失を被ったため、お金に困っている様子だ。マネーマーケットの動揺で損を出した、という記述からすると、リーマン・ショックの後、アメリカのマネーマーケット商品が、通常ならあり得ない元本割れを起こすという事態、 所謂 “broke the buck [6]” 現象が発生 した、2009年頃が本書の舞台設定ではないだろうか。
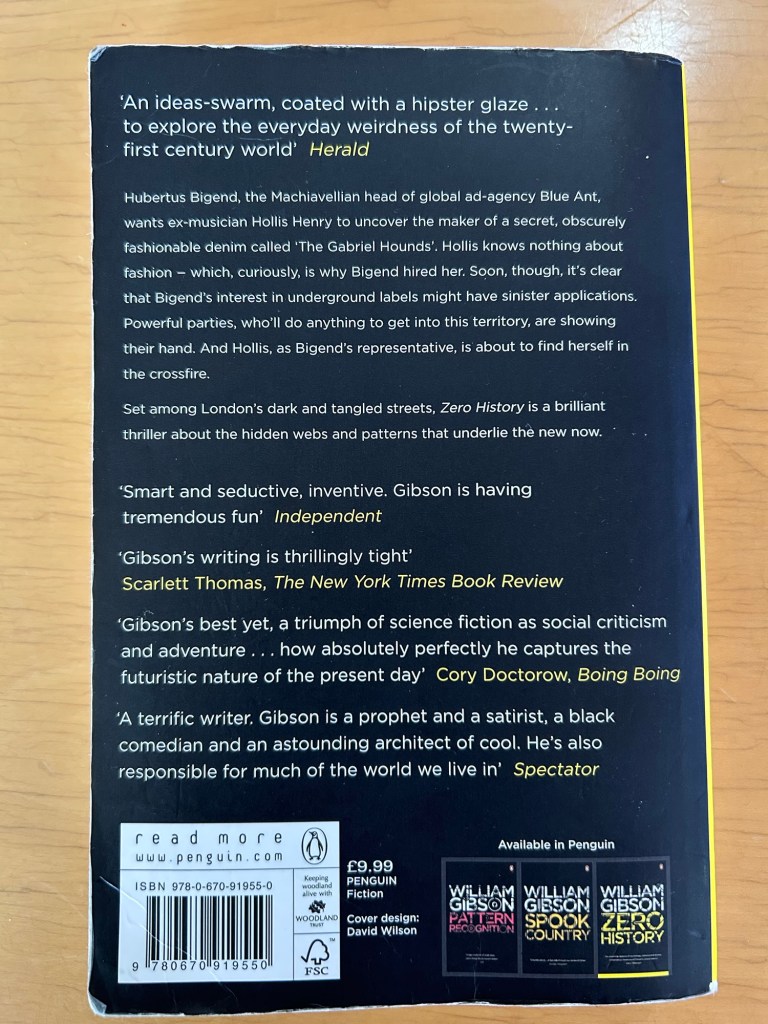
それにしても話の筋をフォローするのが難しい作品だ。場面ごとに、ホリーかミルグリムの視点に切り替わり、そこでホリーもしくはミルグリムが何を見て、何を考えて、何を感じているか、という内容について一人称視点で書かれている。本筋に関係するディテールがところどころにちりばめられている。それを丹念に追っていかないと、登場人物の成り立ちも分からなければ、話の展開も全く見えてこない。本書を一度通して読んだだけでは、さっぱりよく分からなかった。
ただ、そういう表現方法には、エレガンスというか、格好良さも感じた。
全てわかりやすく説明されているわけではないため、登場人物の一人称視点に没入し、その感情や発想から小説の粗筋を読み取っていかざるを得ない。そこにはパズルを解いていくような不思議な中毒性があり、現に自分もやめたくてもやめられない状態に陥り、数回読み直してなんとか物語の輪郭は理解できた気にはなった。
作者は日本贔屓なのだろうか、本書にはやたらと日本が登場する。「ゲイブリエル・ハウンズ」秘密ブランドのジーンズも日本で製作されたものではないか、といった話題もでるし、会話中を含め、日本人[7]が時折登場する。
粗筋を把握するために本書に再度目を通したところ、この作品をSF小説やサイバーパンク小説の一種だ、と高をくくったのが良くなかった、と反省した。読者が行間を埋めながら読めるような自由が確保されているというか、行間を埋めながら読まざるを得なくなるような執筆手法が用いられていて、SF小説というより文学作品と捉えた方が、読んで痛い目に合わずに済む気がする。
本書のタイトルの『ゼロ・ヒストリー』にはどのような意味がこめられているのだろうか。小説中に登場するシークレット・ブランドのゲイブリエル・ハウンズのように、過去の経緯や経歴について把握することが著しく困難な物の事を指すのだろうか。もしくは本書の後半に登場する、監視カメラの目をかいくぐるための技術を活用しながら、足跡を残さず、他人に気づかれず、経歴をゼロにしながら生き延びていく事をさすのだろうか。
自分はこれまで、ギブソンのサイバーパンク小説以外の作品の読書に何度かチャレンジしてみたものの、一度も最後まで読み切ることはできなかったが、本書を繰り返し読むにつけ、2020年に出版された最新作の ”Agency” 等を読んでみたい、と思うようになったし、久しぶりに『JM』を見直してみたくもなった。
なお、本書 “Zero History”は2010年に出版されたものの邦訳版は出ていない。2025年4月現在、ウィリアム・ギブソンの作品は、2008年に邦訳版が出た、本書の前作にあたる『スプーク・カントリー』を最後に邦訳版は出ていないため、本書の後に出た ”The Peripheral” や “Agency”も日本語版は出版されていない。
[1] 「サイバーパンク」は響きがいいので何となく使ってしまうが、具体的にはどのような概念なのだろうか。
ビジュアルなイメージとしては、映画『ブレイドランナー』に登場する街の雰囲気こそがまさに『サイバーパンク』だと思う。ピンポイントで挙げるとすれば、ハリソン・フォードが演じるデッカードが、隣の客と肩をぶつけ合うような、狭い屋台風の店でラーメンのようなものをすすっている場面。街には怪しくけばけばしいネオンサインやらTV広告が乱立していて、地面からは湯気みたいなものが立ち込めていて、暗いけれど美しくもある風景。
そこにあるのは、コンピューター・ネットワーク技術、アンドロイド技術、監視用技術が極度に発達した世界。住民同士のつながりは希薄で、殺伐とした雰囲気が漂う都市空間こそが「サイバーパンク」ではないだろうか。
[2] キアヌ・リーブスや北野武に加え、ドルフ・ラングレンも出演していた。この他にリーブスが出演したサイバーパンク作品としては映画『マトリックス』シリーズと、ポーランドのゲーム会社によるビデオゲーム『サイバーパンク2077』がある。
『サイバーパンク2077』ではプレイヤーが操作する主役キャラクターの分身的存在の声優を務めていて、リーブスの容姿を模したその分身キャラは主役の思考の中に存在し、主役の前に有無を言わせず登場しては主役の行動を小ばかにしながら、しゃべりまくる。膨大な量の台詞の吹き替えを行っている。
なお、『サイバーパンク2077』の続編『仮初の自由』にはキアヌに加え、イドリス・エルバが声優として出演している。
北野武は『JM』の他に2017年の映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』にも出演していて、リーブスほどではないかもしれないが、サイバーパンクと縁があるようだ。
[3] 短編ストーリーおよび映画ともに原題は“Johnny Mnemonic”。
[4] 本書の著者経歴によると、『ニューロマンサー』の販売部数は600万部以上で、ギブソンはその前の短編作品の中で「サイバースペース」という用語を使用し、発明した、とのこと。『ニューロマンサー』、『カウント・ゼロ』、『モナ・リザ・オーバードライブ』は彼の初期の三部作。
[5] ビッグエンドの発言をつなげ合わせてみると、多分このような論理展開と動機だと思うのだが、確信度は70パーセント程度。
[6] 安全性が高いとされるマネーマーケット・ファンドの “The Reserve Primary Fund” が米投資銀行リーマン・ブラザースの破綻後に元本割れを起こした事案。
[7] 本書193頁では、登場人物の一人、ハイジが 、自分が通っている「フジワラ」なる精神科医が日本人だ、という事を語りだし、精神科医をやっていては日本では生計を立てられないのでその医者はロサンゼルスに引っ越してきた、という話をしている。また、治療の一環としてハイジが「ブレスト・チェイサー」なるロボット型プラモデルを作っている、という描写もある。ギブソン氏の出世作『ニューロマンサー』のパートワンの題名は「チバ・シティ・ブルース」だった。日本の事を具体的にどう思っているのかは分からないが、少なくとも関心はあるようだ。
コメントを残す