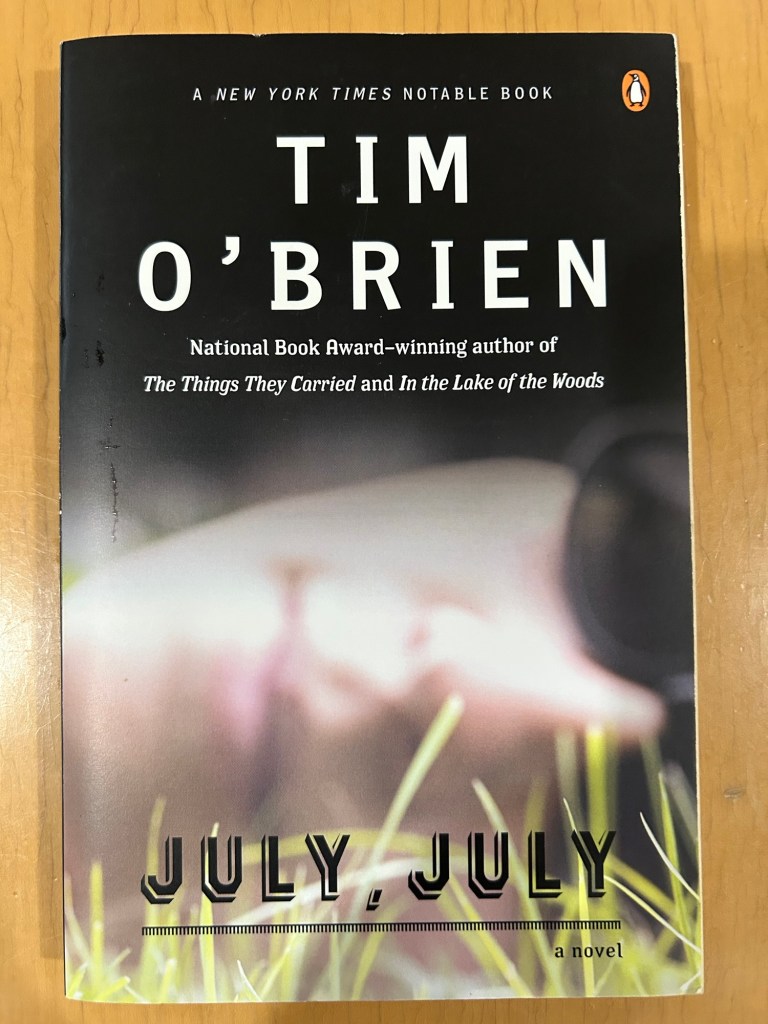
本書『July, July: A Novel』の舞台は2000年の7月7日で、主人公達は1969年に米国北西部ミネソタ州のダートン・ホール大学を卒業し、一年遅れで開催されることになった30周年の同窓会に参加している、という設定だ。参加者は皆53歳前後で、それぞれが就いている職業を列挙すると、弁護士や教師、企業経営者や政治家等、いかにも社会的成功を収めていそうな人達だが、そのほとんどが、どこか現状に対する不満や失望感を抱いている。
世の中的には20世紀最後の年で、ちょうど米国のドットコム・バブルが崩壊してハイテク株は急落し、投資家のポートフォリオは棄損していた[1]、とのこと。その前年に同級生カレン・バーンズが殺人事件に遭い、帰らぬ人となるなど、どこか物悲しく荒んだ雰囲気のなか執り行われる同窓会である[2]。
さて、著者のティム・オブライエンは小説家としてデビューする以前は、1969年から1970年にかけてベトナム戦争に歩兵として従軍し、その後ハーバード大学院で学んだり、ワシントン・ポストで記者を務めたりした経歴の持ち主である[3]。
1979年には『Going After Cacciato』(『カチアートを追跡して』)でアメリカの芥川賞と直木賞を合わせたようなNational Book Awardにおいて、ジョン・アービングの『The World According to Garp』(『ガープの世界』)などに競り勝ち[4]、フィクション部門で受賞し、1987年にエスクァイア詩で発表した短編の 『The Things They Carried』でNational Magazine Award のフィクション部門で表彰されるなどして知名度が上がった。これら二作を始めとして、オブライエンの作品には自身のベトナムでの従軍経験が色濃く反映されているものが多い[5]。2023年には20年ぶりの長編小説で、トランプ政権時代のアメリカの風潮を風刺した『America Fantastica』(『虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ』)[6]を発表し、話題になった。

いかにもオブライエンの作品らしく、本作の主人公の一人、デイヴィッド・トッドはベトナム戦争に前線の兵士として従軍した際に足を負傷し、その後障害と共に生きてきた人物だ。
その負傷からくる、デイヴィッドが感じた壮絶な痛みと苦しみについての描写は、読んでいて悪寒を感じるくらいに凄まじい。こんな経験は絶対にしたくない、と思わせられた。当時のデイヴィッドの夢は大学の同級生のマーラ・デンプシーと結婚することで、その願望を支えに負傷に耐えベトナム戦争を生き延び、帰国後にマーラと結婚したものの、二人は九年後[7]に別れる。
デイヴィッドは、その後もマーラと一緒に過ごしたいとずっと願い続けている一方、マーラは個人主義の塊のような人物で、デイヴィッドに対し好意を抱きながらも、昔から彼女にとって最も大切なのは一人でいることだった。
従軍して帰国した人間は筆舌に尽くしがたい経験をした一方、従軍する事を避ける為に国を捨てた人間は、また違った形で一生消せない傷を負うこととなった。
ベトナム戦争に反対し、兵役に召集するのを避ける為、隣国のカナダのウィニペグ市に移住する事を選択したのはビリー・マクマンである。その当時、付き合っていたドロシー・スティアもついてくると信じていた彼の思いは成就せず、彼女はアメリカそして家族の元に残る事を選択する。
1969年にカナダに渡ったビリーは、アメリカに戻れば兵役召集を忌避した犯罪人である。二度と故郷にもどれない事を覚悟した彼は、ドロシーから別れを告げられ、恨みを募らせる。1974年にはカナダで市民権を得てその翌年には結婚する。それでも、いつかドロシーの気が変わり自分と一緒になってくれるのではないかという淡い期待を捨てきれないまま年月は過ぎる。身勝手で、自己中心的なビリーだがその境遇は哀れで気の毒に思えて、読んでいて同情を禁じ得ない思いがした。
本書はこのような個性的なキャラクターが数多く登場する小説である。スプーク・スピネリィは男にモテまくる女性で、男性二人と結婚している。法律上の夫は一人で、もう一人は事実婚とでもいうのだろうか、法律で認められた配偶者ではない。それでもスプークは二人の間をいったりきたりしながら生活していて、しかも二人の夫同士も話会い、その不思議な三角関係を続けていくことで合意済みという、にわかには信じがたい関係性である。
マーヴ・バーテルは学生の頃からスプークに好意を寄せていて、二度の結婚と心臓の手術を経た今でも、いつか一緒になる夢を捨てきれないでいる。
数奇で衝撃的な経験をしてきた登場人物は他にも登場し、皆なにがしらのトラブルや悩み、自責や後悔の念を抱えながら生きている。せめてこの二人だけでもハッピーになれるのか、いやそんなことはこの小説の展開からしてあり得るのだろうか、とハラハラさせながら、ストーリーはクライマックスへと向かっていく。
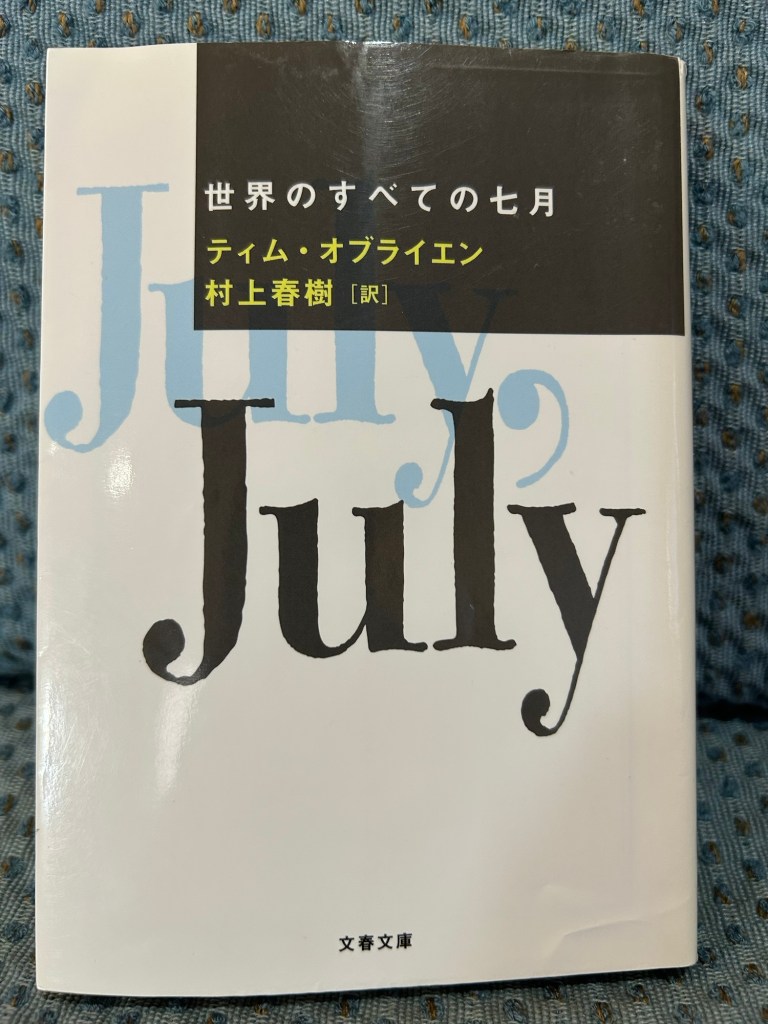
五十代前半はここまで大変な年齢なのか、と愕然とさせられる作品だ。悔いのない人生を生きることの難しさ、むしろ後悔はつきもので生きてきた証ではないか、という現実の難しさや厳しさ、そして読みながら平和の有難さを実感する作品でもある。
この小説がベトナム戦争についてそうしているように、アジア・太平洋戦争のあと20年~30年経ってから戦時中を振り返る、という設定の日本の小説があれば、是非一度読んでみたいと思う。戦争を体験した人にとって、1970年代や1980年代の日本はどのように映ったのだろうか。
[1] 本書、9頁:”Techs were tumbling. Portfolios were in trouble.”
[2] 本書、7項:“Death, marriage, children, divorce, betrayal, loss, grief, disease: these were among the topics that generated a low, liquid hum.”
[3]オブライエン氏の経歴は次の本を参照した。“The Things They Carried,” Tim O’Brien, Flamingo, London, 1991 (First published in Great Britain in 1990 by Collins), author biography.
[4] National Book Foundationウエブサイトの1979受賞作品のページでフィクション部門にクリックすると受賞作品と最終選考に残った作品が表示される。なお、『ガープの世界』は1980年のフィクション、ペーパーバック部門で受賞している。 https://www.nationalbook.org/awards.prizes/national-book-wards-1979/
[5]自分が著者の作品と出会ったのは “The Things They Carried”が短編集として出版された1990年代前半の頃。
[6]残念ながらまだこの最新作は読めておらず、内容の紹介はニューヨーク・タイムズの書評記事を参考にした。本当はこの最新作を読んで書評を書きたかったのだが、まだ高価なので断念した。“Lying All the Way to the Bank in ‘America Fantastica,’” By Noah Hawley, New York Times online edition, Oct. 23, 2023, accessed on July 27, 2025.
[7] 本書、13項。
コメントを残す